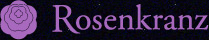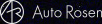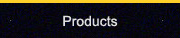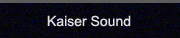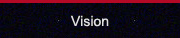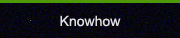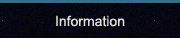���{�o�ϐV�� 2014/8/18�@�_�C�������h�̐l�Ԋw�i�L�V�����j
161�L���Ȃ�0.38�b�Ńz�[���x�[�X�ʉ�
�s�b�`���[�}�E���h�̃v���[�g����z�[���x�[�X�܂ł�18.44���[�g���B���������J�������悻1.44���[�g�����ݏo���ē������Ɖ��肷��ƁA�P���v�Z��0.38�b�Ń{�[�����z�[���x�[�X��ʉ߂��邱�ƂɂȂ�B
�l�Ԃ̖ڂ́u���v��ʂ��āu������v�Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă���̂����A������܂łɂ͎��Ԃ�������B������f����������A�t�H�[�J�X(�œ_)�������܂Ŗ�0.1�b������Ƃ����Ă���B
�ؓ��͔]����̔���ȓd�C�M���ɂ���ē����B�܂�A��⑫�Ȃǂ̋ؓ��͂��ׂāA�]����̖��߂ɂ���ē����̂����A����ɂ����Ԃ�������A�ؓ��������܂łɃg�b�v�A�X���[�g�Ŗ�0.1�b������̂��B
���Ȃ݂ɁA�����̔\�͔͂N���ǂ����Ƃɒቺ���A�œ_�����킹����A�ؓ������Ƃ������]����̓`�B�X�s�[�h�ɂ��e����^����B�v���̑Ŏ҂�������Ƃ������Ƃ̗͑͂�C�͂̐�����肱�������\�͂̐����������̂����A�c�O�Ȃ��Ƃ�30�`40�Α�ł͂��������\�͂̐����Ɏ��o�ǏقƂ�ǂȂ��A�������ƋC�Â��I��͏��Ȃ��B
140�L���̑����ł�0.1�b�Ŗ�3.8���[�g�����{�[���������A0.01�b�ł�38�Z���`�����킯�ŁA�킸���Ȑ������o�b�g�R���g���[���ɉe����^����͓̂��R�Ƃ�����B
160�L�������Ă��s�퓊��̕s�v�c
�b��߂��ƁA160�L�����鑬���ɑ��Ắu������v�܂ł̎��ԂƁu�łāv�Ɣ]���M���𑗂鎞�Ԃ����ł�0.2�b�������Ă��܂��A���̏u�Ԃɂ͂��łɁA�{�[���͓��聨�ߎ�Ԃ��ȏ�߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B
���̏����őŎ҂́u���p�E�O�p�v�u���߁E��߁v�u�X�g���C�N�E�{�[���v�u�łE�ł��Ȃ��v�Ƃ������f������킯�ŁA�����Ɏc���ꂽ�킸���Ȏ��Ԃ��l����ƁA������160�L���̑�����łƂ������Ƃ�����̋Ƃ��킩���Ă��炦�邾�낤�B
����ȋ����Ȃ��ȒP�Ƀo�b�g�ɓ�����̂��A�s�v�c�Ɏv���l�͑����Ǝv���B�R���̑�J�͂V��𓊂��ĂX���ŁA�Q���_�B���q�\��A���{�����ɓK���ł��i���A10����O�ɑ����݂ƂȂ����B
�V��Q���_�Ƃ������Ƃ́A�攭����̐ӔC���ʂ��������ƂɂȂ邪�A150�L����㔼����160�L���̋���A�����Ȃ���o�b�g�ɓ��Ă��A���̏�s�퓊��ɂȂ邱�Ƃ�s�v�c�Ɏv���l�������͂����B
����ŁA�Ⴋ���̒����E�R�{���̂悤��130�L���䔼�̋��ł��ő����ɂ��ő��D�O�U���ɂ��P�����Ƃ�����B���Ƃ��s�v�c�Ȃ��Ƃł���B�����ɂ͖싅�I��̓r�����Ȃ��D�ꂽ�\�͂��B����Ă���B
���̌��ۂ��������O�Ɉ�����f���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A160�L�����鑬���𓊂�����l�Ԃ͐q��ł͂Ȃ��\�͂̎�����ł���Ƃ������ƁB160�L�����̑����̓v���̖ڂ��猩�Ă����l�I�ł���B
�Ō��́u�\���v�̉��ɐ��藧���
�ł́A�Ȃ�160�L���̋��𓊂��铊�肪�����A130�L����̋��𓊂��铊�肪���悤�Ȍ��ۂ��N����̂��A���̓����͑Ō��Ƃ�����Ƃ��u�\���v�̉��ɐ��藧���Ă��邩��ł���B�����ł����\���Ƃ͋����R�[�X�ɂ��炩���ߓI���i��悤�ȍs�ׂł͂Ȃ��B
�����ƒP���ȗ\���ŁA�ȒP�ɂ����Ɖߋ����疢����\������s�ׂ̂��Ƃł���B����̎茳����{�[��������R���}���b���̎��_�ŁA�ǂ�ȋ���łǂ̃R�[�X�ɗ��邩�A����Ɠ����ɃX�g���C�N���{�[�����A�����đł��ł��Ȃ������f����ꏊ������B���̃G���A�őŎ҂́g�����h��\������̂��B
���Ƃ����͋�C��R�ŕK���������邵�A�d�͂�����̂Ō����ɂ����ǂ�ȃ{�[�������ނ��ƂɂȂ�B�����̂��Ƃ��u���Ɍv�Z���āu���Ԃ���ʉ߂��邾�낤�v�Ǝv����Ƃ���Ƀo�b�g��U��o���B�܂�A�ߋ����瓾�������u���ɕ��͂��āA������\�����Ă���̂��B
�Ŏ҂͂��̗\���s�ׂ��A���N�싅�̂��납��A������A�Ђ���Ƃ���Ɖ��S����ƌJ��Ԃ����o���Ɋ�Â��čs���Ă���B�������A���̔\�͓͂w�͂�������ΒN����������\�͂ł͂Ȃ��B�I�ꂵ�l�Ԃ��A���X�Ȃ�ʓw�͂����ē�������̂Ȃ̂ł���B
�Ŏ҂̗\�������鋅������̂��D����
�Ƃ��낪�łv�����������œ�����v�������݂���킯�ŁA�Ŏ҂���������w�͂��ē����\���̔\�͂����킷���肪�����B�ʂĂ��Ȃ��w�͂ƌo���̏�ɐ��藧�Ŏ҂̗\���s�ׂ��鋅�𓊂��铊�肱�����D����Ƃ������Ƃł���B
���̈Ӗ��ő�J�̑����͑Ŏ҂̗\���ʂ�̋����ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B�������A�����͒��l�I�Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ��Ή����Â炢���Ƃ͊m�������A������x�Ŏ҂̗\���ʂ�ɗ���̂Ńo�b�g�ɓ�����̂��B���ɑ�J�̋���150�L���ɖ����Ȃ��X�g���[�g�ł���v���̑Ŏ҂͂����Ɨe�Ղɑł��Ԃ��Ă��邾�낤�B
�]�k�����A��������̎肩�痣��āA�Ŏ҂������Ȃǂf��������\������ꏊ�̂��Ƃ����́u�e�]�[���v�Ɩ��t���Ă���B����ɖ��t���Ă��܂������A���܂ł��̑厖�ȃ]�[���̂��Ƃ�N���l�[�~���O���Ȃ������̂͂ނ���s�v�c�Ȃ��炢���B���ꂭ�炢���̃]�[���͑Ŏ҂ɂƂ��đ厖�ȃ|�C���g�Ȃ̂��B
�Ŏ҂ɂ���Ă܂��܂��̂e�]�[��
�e�]�[���̂e�̓t�H�[�J�X�̂e�B���ɏœ_�����킹�Č���߁A�o�b�g��U�邩�U��Ȃ����̌��f�������]�[��������e�]�[���B�ł́A���̂e�]�[���Ƃ͈�̂ǂ̂����肩�Ƃ������ƂɂȂ邪�A����͑Ŏ҂ɂ��Ƃ��������Ȃ��B�����A�e�]�[�����z�[���x�[�X���A�܂�Ŏ҂ɋ߂���߂��قǁA�D�ꂽ�Ŏ҂��Ƃ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�e�]�[����������A�܂�Ŏ҂��牓���Ȃ�Ȃ�قǗ\�z�Ǝ��ۂ̌덷���傫���Ȃ�m���������Ȃ�B���ɋ��̔��f�����肬��܂Œx�点�āA�茳�ɂЂ��t���邱�Ƃ��ł���Ό덷���������ł���B����ɂ͑Ŏ҂̃o�b�g�X�s�[�h��o�b�g�̃w�b�h������肵�Ȃ��Ȃǂ��낢��ȗv�f���W���Ă���B
2000�N�̓��{�V���[�Y�͒����ΗY�ē����鋐�l�Ɖ��厡�ē�����_�C�G�[�Ƃ́u�n�m�Ό��v�ƂȂ����B�����A�_�C�G�[�̐��ߎ肾�����铇���i�����l�̎�C����G���ŐȂɌ}�����Ƃ��̘b�ł���B
�Ŏ҂̗\�z�ƌ덷���Ȃ��H��J�̋�
�_�C�G�[�̓��肪�ǐ^�Ƀ{�[���𓊂��Ă��܂����B���̏u�ԁA�铇���u�����v�Ɛ����o�������ȊÂ��{�[���������Ƃ����B�Ƃ��낪����̓o�b�g��U���Ă��Ȃ������B�铇���u�ǂ������A�������Ă��ꂽ�v�Ǝv�����u�ԁA����̃o�b�g���ڂ̑O�ɏo�Ă��Ă��̂̌����Ƀz�[�������ɂ����������B�铇�́u���̃^�C�~���O�Ńo�b�g���o�Ă���o�b�^�[�͏��߂Ă��v�ƌ������Ă����B
���̃V���[�Y�A�R�{�ۑłW�œ_�łl�u�o�ɋP��������̂e�]�[�����A���̏铇�ł��r�b�N������悤�ȋ߂��������Ƃ������Ƃ��B
��J�̒����قǂ̃X�s�[�h������A�ǂ�ȑŎ҂ł��ʏ���e�]�[���͓�����ɂȂ�͂����B�܂�A���ʂ̓����葁�߂ɐU�邩�U��Ȃ����̌��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̊��ɋ�U�肪���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A��J�̋����Ŏ҂̗\�z�Ƃ̌덷�����قǐ��܂Ȃ������Ƃ������Ƃ������悤�B�������A�J��Ԃ��ɂȂ邪�A160�L�����鑬���𓊂�����l�Ԃ͐_����I�ꂽ�l�Ԃł���Ƃ������Ƃ͋������Ă��������B
�\�����Â炢���A���@�_�m������c
���Ȃ݂ɁA���̔��̃{�[���𓊂���A�܂�A�\�����Â炢�{�[���𓊂��铊��̑�\�I�肪���싅���i�J�u�X�j�ł���B��_����̓���̓I�[���X�^�[��Ńp�E���[�O�̋��Ŏ҂�������{�ŋ��������B��������ΓI�ȃX�s�[�h�����������A����ȏ�ɔނ̓����鑬�����Ŏ҂ɗ\�z�𗧂Ă邱�Ƃ��狖���Ȃ������̂��B
����܂ł͂����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����悤�ȗ\�����Â炢�{�[���𓊂��铊��Ƃ��ď㌴�_���i���b�h�\�b�N�X�j�A�����r�Ɓi���l�j�A�a�c�B�i�J�u�X�j�A�R�{���A�\���Ďj�i��_�j�炪��������B���ׂ�160�L���̑����͓������Ȃ����A�O�U��D���铊��ł���B�ނ炪�ǂ̂悤�ȕ��@���g���ė\�����Â炢�{�[���𓊂��Ă���̂��́A���͒肩�ł͂Ȃ��B
���͖�23cm�A�d��147�O�����O��̋��̂��ǂ�����A�\�����Â炢�����ɂȂ�̂��A�싅�E�ɂ͂��܂����̕��@�_���m�������l�Ԃ͂��Ȃ��B
�ƂȂ�Ƌ�C�͊w�Ƃ����������̐��ƂɁA���̓��������߂邵���Ȃ��B�����A��J�������̐��Ƃƃ^�b�O��g�߂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��N���蓾��B�����A���̂悤�ȕ��@�_���m��������140�L���̑����ł��\���Ƀv���싅�E�Ŋ���ł���Ƃ������ƂɂȂ�͂����B���̖��̂悤�ȕ��@�_���m�����������҂��������B
�L�V�����i�싅�]�_�Ɓj
�I�[�f�B�I�A�X���[�g�̎��ɂƂ��āA
����قǃI�[�f�B�I���i�̐v�ɖ𗧂��͂͂Ȃ��B
����f�[�^�[�̐Ó����Ǝ���̓������ƌ�����B